自分用に作ったマルチ型スマホケース。
気にいってはいるんですが、手帳型は使いにくい。
というか、使い慣れてない。
どうも、八幡です。
今までスマホは、プラケースにスマホリングをつけて使用していました。
手帳型はスマホリングを付けられないことが弱点ですね。
使い慣れたスマホケースを、レザークラフトで作れないかチャレンジしてみました。
とりあえず完成品はコチラ。

結果的には「半分成功、半分失敗」ですね。
必需品
MDFボード
こんな感じの板になります。
今回の自作のキモになります立体成型。その立体成型の内型に使います。
軽くて加工しやすいので、とても便利。
百均にも置いてあるので、そちらで充分ですし、安いと思います。
カシメ
12mmコンチョ
お好きなコンチョで作成しましょう。
制作過程一覧
- 立体成型の内型と外型の作成
- 立体成型
- レザーバーニング
- リングベルト部分作成
- カシメうち&コンチョ取付け
- カメラ用&ボタン用の穴あけ
- プラケースへの貼付け
- コバ処理
制作過程
いつもなら、作成過程でめずらしい部分だけ書いています。
しかし、今回は初挑戦も多いので、ほとんどの過程を書くことになりそうです。
今回の初挑戦は何と言っても「立体成型」。
立体成型とは革の持つ「可逆性」を利用した技法です。
「絞り技法」、「ウエットフォーム」などと言ったりもします。
ヌメ革を水に濡れた状態で力を加えると、その形のまま締まって固まってしまいます。
こんな感じのカービングや、ポーチの角部分のカーブを成型するために行います。
濡れた革を型にはめたまま乾かすことで、型通りの革を成型することができます。
1、 立体成型の内型と外型の作成
立体成型をするために、まずは型をつくります。
型を作る材料はこちら。

必需品に載せたMDFボードと棒と梱包用フィルムです。
全て百均品。
今回、梱包用フィルムは使いませんでしたが、使った方が良かったなぁ。
まずはMDFボードで内型を棒で外型をつくります。
ちなみにソーガイドを使って切りました。
木工用制作ソフト「もりでん」のために買ったソーガイドですが、ガイド自体も良いですね。

ブレようがありませんからね。
ノコギリで真っすぐ切れたことのない八幡でも、真っすぐです。
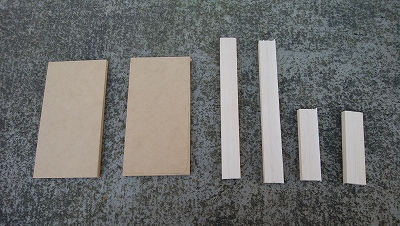
お陰でこの通り。
ボードを内型にするには厚さが足りないので、ボンドで2枚貼り合わせて使います。
そしてサンダーで面取り。
特に角は革の形に直結してくるので、丁寧に整えます。
外型は釘で打ちつけます。
久々に使いました。
いつもはインパクトドライバーとビスを使用しているので…

立体形成は乾いた時に1~2回り縮むので、内型はプラケースより一回りほど大きくしておくとよいと思います。
でも、これは少し大きすぎるかな?
写真では分かりにくいですけど・・・
2、立体成型
型が出来たら、次は革に水を染みこませます。

染色も何もしていないヌメ革ならスグに水が染みこみます。
一応5分もほど待ちましたが、3分でも多いくらい。

内型に乗せて、スリッカーで周りを押し付けます。
簡単なものなら、押し付けるだけでもいいのかも。
しっかりと形を保ちたいなら、やはり外型も必要です。

型をクランプで固定して、そのまま放置して乾かします。
1日くらいは必要。
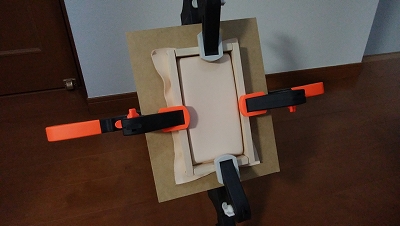
乾くと革の色は元通り。
でも、形は御覧の通り。


型を外しても形は崩れません。
これが立体成型。
3、レザーバーニング


4時間もかけてレザーバーニングしました。
使用したのは、もちろんいつものマイペンアルファです。
細かすぎたなぁ。
0.5B型が細かい模様を描くのに適した、一番細いペン先。
全部見せられないのが、残念です。
細かくバーニングしたのが伝わっていれば幸いです。
4、リングベルト部分作成
「リングベルト」って勝手に名付けた部品名ですが、スマホリングの代わりにするためのベルト状の部品です。
ちなみにスマホリングとはこれ。
スマホの落下防止とスタンドとしての機能があります。

リングベルトは強度も必要なので2mm厚の革を用いました。
まずはカシメとコンチョのための穴を空けました。
そして切れ込みを入れます。
切れ込みを入れることでスライド式にして、指の入る隙間を調整できるようにしました。
5、カシメうち&コンチョ取付け

本体にもカシメとコンチョ用の穴を空けます。
ちなみに穴を空ける時に脇が邪魔だったので、切ってしまいました。

最初、ベルトの固定は両穴ともカシメを使う予定でした。
しかし実際やってみると、本当に固定されちゃいました。
スライド式に出来ない。
なのでネジ式のコンチョにしました。

これで微調整可能!
実際にコンチョにしようと決めたのは、ボタン用の穴を空けた後なので、写真は前後しています。
ご容赦を。
多分、何枚か前後する写真があるかも。
6、カメラ用&ボタン用の穴あけ

デザインナイフを使って穴を空けます。
どうしても切り口がブサブサになってしまうので、小型のヤスリで出来るだけ整えます。
整えた後は穴のコバ処理。
小さい穴に水やトコノールをつけるのには、綿棒が便利。

そしてスリッカーでゴシゴシ。
7、プラケースへの貼付け
ココまで作成した本体とプラケースとを貼り合わせます。
でもその前に...

薄くオイルを塗り込みます。
これで少しは汚れがつきにくくなるかな?
このオイルは革細工用品店の革専用のオリジナルオイル。
お手入れにも使えるようです。
本当はカシメを付ける前に塗れば良かった。
ちなみにベルト部分はスライドしやすいよう、切れ目などに微調整を加えています。
さらにベルトにもレザーバーニングを施しています。

貼り付ける前にプラケース(正確にはシリコンケース)を脱脂します。
脱脂はアルコールで清拭するだけでOK。
脱脂をしておけば、テープや接着剤の貼り合わせが強力になります。

面部分は両面テープ、側面は接着剤のGクリアーで貼り合わせ。


ここで失敗。
というか、立体成型の段階で失敗していました。
型枠がプラケースより余裕を持ち過ぎていました。
なので革が縮んでも、革の本体とプラケースの間に隙間が…
その結果、文字通り「しわ寄せ」が来ました。
ピッタリ貼り合わない(*_*;

仕方ないので、シワ部分は切り取ることに…
残念。
8、コバ処理

まずはヤスリをかけて、余分な部分を削り取ります。
そしていつものように磨きます。

気が済むまでコバを磨いたら完成です。
完成品

完成したスマホケース。
ただ革を貼っただけではなく、ベルトを取り付けることで機能も獲得しています。

指を入れると落下防止機能。

机や床に立てるスタンド機能にもなります。
どや!
ただし、失敗したところも幾つか。
- 立体形成時の隙間の大きさ
このせいで貼り合わせの時にしわ寄せが…
- ボタン穴の小ささ
ボタンが押しにくい。
というか、押せませんでした。
後で穴を広げて調整しましたが…それでも押しにくい。
ボタン穴は余裕をもって大きめに。
- スリッカーの汚れ
小物しか作っていない八幡のレザークラフト。
とはいえそれなりの数を作ってきました。
そのせいでスリッカーもそれなりに汚れが...
そのスリッカーで磨いていたら、汚れがコバについてしまいました。
まとめ
使いやすいスマホケースにしたつもりですが、使っていく中でまた課題も出てくるでしょう。
そしたら、また考えて改良しながら作ろう。
とりあえず、立体成型を上手く調整できれば、プラケースに貼り合わせなくても革だけでケースが作れそう。
型枠の固定は梱包フィルムを使って、包む様にすれば内側を向いて固まるから、ケース状に出来そうです。
調整は難しそうですが、挑戦する価値はありそう。
挑戦時期は未定ですが…
いつになることやら・・・

0.1mm単位の大きさに拘らなくていいなら、立体成型はあまり難しくありません。
例えばポーチなどの小物入れを作成するには丁度いいかも。
参考になるサイトはそれなりにあるので、皆さんも挑戦してみてください。
八幡でした。





